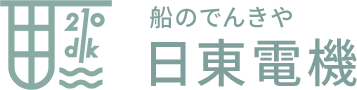ブラケットライト・照明器具に関するコラム
ブラケットライトを取り入れてオシャレな空間を演出しませんか?
ブラケットライト・屋外照明器具・真鍮セードのお求めは「船のでんきや日東電機」へ
| 会社名 | 有限会社 日東電機(Nitto Electric Ltd.) |
|---|---|
| サービス名 | 船のでんきや日東電機 |
| 設立 | 法人化1989年4月1日 / 創業1951年 |
| 所在地 | 〒928-0071 石川県輪島市輪島崎町1−78−161 |
| Tel | 0768-22-0543 |
| Fax | 0768-22-4047 |
| メール | info@210dk.com |
| 営業時間 | 月曜~土曜 8:30~17:30 (祝祭日 除く) |
| 定休日 | 日曜日・祝祭日 |
| URL | https://210dk.com/ |